

|
||
| 釣針状の野付半島に抱かれた内湾を野付湾(のつけわん)と呼びます。 面積48平方キロメートル余りの湾となっています。 湾内には数条の潮切りが走り、全般に海草が繁茂する2、3mの砂底にあって、 アサリ・ホッキが生息し、潮干狩の好適地となっています。 また、夏には三角帆のエビ曵船が点在し、冬には氷下漁の光景がみられます。 11月〜3月にかけては、白鳥が群舞し、波間にはオットセイのおどけた姿などと、 四季おりおりの風物詩にはこと欠かない。また、シーズンには遊覧船も就航します。 |
Map |
|||
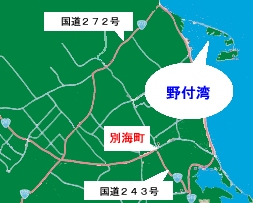 |
|||
 |
| 【打瀬漁】 えび漁は、野付湾(尾岱沼)の開拓とともに始められたようで、明治20年頃から、約7mの磯舟を網につなぎ、錨止めして50〜60mの網を、手引き或いは手巻きで操業していたが、風のあるときには舟が流れてしまうことから帆を張り、誰が始めたということもなく帆を利用する漁法となった。漁具の形は当時も現在のものもあまり変化はなく、材質が化学製品に変化した程度で現在も行われている漁業である。 この漁業は、野付湾内を漁場として行われている。水深は1〜3mと浅く、底質は泥場であるが、一面にコアマモ及びアマモが密生して、その藻場がエビ類の生息漁場となっている。湾内では、アマモ類の繁茂のみられない場所にはエビの生息は認められない。北海シマエビは、5〜6月に孵化し、満1年で体長6cm、2年で10cm前後に成長し、雄として成熟する。3年では12cmとなり、一部は性の転換をして雌となる。 |