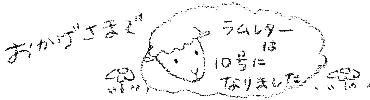拑楬傔傫梤杚応曋傝LAMB LETTER
|
|
2000擭偺僥乕儅偼儌儞僑儖 仧儌儞僑儖偐傜偺媞恖仧 丂偁傞擔変偑壠偺尯娭偵儌儞僑儖堖憰偵恎傪曪傫偩抝偑尰傢傟偨丅傛偔尒傞偲10僇寧慜偵儌儞僑儖僿椃偩偭偨庰堜孨偩偭偨丅斵偼娽傝側偔儌儞僑儕傾儞偵嬤偄僕儍僷僯乕僘偱偼偁偭偨偑丄僑價偺憪尨偵棫偮梀杚柉偺巔偑儚乕僾偟偰栚慜偵尰傢傟偨偺偩偐傜丄堦弖丄擔杮岅偱惡傪妡偗傞偙偲偵鏢鏞偟偨丅庰堜孨偼丄巹偑戝妛棧戙偵嶌偭偨梤岲偒偺拠娫偺僒乕僋儖偱偁傞乽僔乕僽僋儔僾乿偺屻攜偱丄懖嬈屻丄梤偺杚応偵嬑柋偟偰偄偨偺偩偑丄梀杚柉偺惗妶偵摬傟偰丄壗偺棅傝傕側偄傑傑斵偺抧傊搉偭偨丅儌儞僑儖岅偺抦幆偼丄峴偒偺旘峴婡偱撉傫偩杮偩偗偲偄偆柍杁側椃偺巒傑傝偱偁偭偨偑丄尰抧偱弌夛偭偨恖乆偵悽榖偵側傝側偑傜梀杚抧偱梀杚柉偲堦弿偵曢傜偟偰偒偨偲偄偆丅斵偼擔杮偵偄偨帪偐傜梤偺媺偄偵偼姷傟偰偄偨偑丄帇抧偱偼攏傗梤傗嶳梤偺擕傪嶏傝丄攏偵忔偭偰梤傪捛偄丄僎儖偵怮婲偒偟偰丄暦嫃偟偰偄偨偍攌偝傫偺榙偄傪扴摉偟偰丄媞恖偲偟偰偱偼側偔丄壠懓偺堦恖偲偟偰曢傜偟偰偒偨丅偨偭偨堦斢偺榖偱偼丄偲偰傕暦偒懌傝側偄丄愮栭堦栭暔岅偺傛偆側懱尡択偱偼偁傞偑丄儕傾儕僥傿乕堨傟傞傾僋僔儑儞傪岎偊偨榖偐傜偼晽宨傗恖乆偺摦偒偑尒偊偰偔傞丅巹偵偼梀杚柉偵懳偡傞梤帞偄偲偟偰偺嫟捠擣幆偑偁傞偺偱丄姶妎揑偵揱傢傞傕偺偼戝偒偐偭偨偺偩偑丄斵偺榖偺堦晹傪徯夘偡傞偙偲偵偡傞丅 仧仧帺慠偵崌傢偣壠抺偵崌傢偣傞儌儞僑儖偺惗妶仧仧 丂梀杚柉偺惗妶偼廃傝偺帺慠偲梈崌偟偰夁嫀偐傜偺孞傝曉偟傪椵乆偲愊傒廳偹偰偄傞傛偆偩丅擔偑徃傞偲巇帠傪巒傔丄壠抺偺摦偒偵幧傢偣偰恖偑峴摦偟挬丄嶏擕傪廔偊傞偲梀杚偵弌偟丄攏偵忔偭偰孮傟傪捛偄側偑傜丄擔杤傑偱婣傟傞斖埻傪峴摦敿宎偲偡傞丅憪尨偺憪偼丄擔杮偺傛偆偵娗棟偝傟偨杚憪抧偲斾傌傟偽傑偽傜偵偟偐惗偊偰偄側偄偑丄奀尨偺傛偆偵峀偑傞憪尨偺峀偝傪峫偊傟偽壠抺偺悢偵梋傝偁傞偽偐傝偱偁傞丅廧傑偄偼暘夝堏摦壜擻側栘偺僼儗乕儉偲僼僃儖僩偐傜弌棃偨僎儖偲屇偽傟傞僪乕儉宆偺僥儞僩幃廧嫃偱偁傞丅僎儖偼寛偟偰慹枛側傕偺偱偼側偔丄暘岤偄僼僃儖僩偑壞偺弸偝傪幷抐偡傞偟丄-40亷埲壓偺搤偺姦偝偺拞偱傕儅僉僗僩乕僾堦戜偱抔偐偔曐偰傞悽奅堦僔儞僾儖偐偮崌棟揑峔憿偺斵摍偺儔僀僼僗僞僀儖傪徾挜偡傞廧戭偩丅丂怘惗妶偼壞偼擕惢昳丄搤偼擏偑庡懱偱偁傝丄彫敒暡傪楙偭偰丄僂僪儞傗僷儞丄儃乕僘偲偄偆擏埻巕偺旂傪嶌傞丅彫敒暡偼峸擖偡傞偑丄偦偺懠偼帺媼帺懌偱偁傞丅擏偼傗偼傝梤偺擏偑堦斣懡偄偑丄屲抺偲屇偽傟傞梤丄嶳梤丄攏丄媿丄儔僋僟偡傋偰偺擏傪怘傋丄撪憻丄寣塼丄摢偵偄偨傞傑偱丄巆偝偢怘嵽偲偡傞丅埲慜丄庰堜孨偲偄偭偟傛偵懱尡偟偨偙偲傕偁傞丄儌儞僑儖幃搄嶦曽朄偼丄嬝崪偺壓偺嫻偺拞怱晹偵庤偑擖傞偩偗偺暆偺愗儕儘傪奐偗丄偦偙偐傜庤傪暊晹偵擖傟丄墶妘枌偵偦偭偰攚崪傑偱払偡傞偲丄攚崪偺撪懁傪憱傞懢偄寣娗偑偳偔偳偔柆懪偮偺傪姶偠傜傟傞丅 仧仧仧梀杚柉偐傜妛傇偙偲仧仧仧 丂巹偼堦斢丄庰堜孨偺岅傞榖傪暦偄偰丄崱傑偱壗偲側偔憐憸偟偰偄偨梀杚柉偺惗妶傪娫愙揑偱偼偁傞偑丄敡偱姶偠傞偙偲偑偱偒丄偦偺偙偲偼梤帞偄傪栚巜偟偨摉弶偺棟憐偲尰嵼偺僊儍僢僾傪慛柧偵偟偰丄崱偺擔杮恖偑婥晅偄偰偄傞偐丄偄側偄偐暘偐傜側偄偑丄擔杮傪娷傔偨愭恑崙偲偄傢傟傞幮夛偑書偊傞栤恊偵懳偟偰偺摎偊偺巺岥傪嫵偊偰偔傟偰偄傞傛偆偵巚偊偨丅庰堜孨偼儌儞僑儖偺梀杚惗妶偱丄帺慠偺拞偱偺惗妶偺寖偟偝傛傝傕丄備偭偨傝偲偟偨帪娫偺棳傟偺拞偱梋桾傪姶偠偨偲偄偆丅偦偟偰抦傝摼偨偺偼丄乽懌傝偨傞傪抦傝丄柍懯傪梸偣偢乿偲偄偆恀棟偩偭偨偲偄偆丅梀杚柉偺惗妶偺棳傟偼丄帺慠偺偦傟偵増偭偰摦偄偰偄傞偑丄変乆偺惗妶偼帺慠偺棳傟傪曄偊偰傑偱傕憂傝弌偟偨僞僀儉僗働僕儏乕儖偵傛偭偰丄傔傑偖傞偟偔摦偐偝傟偰偄傞丅梀杚柉偼崱偺惗妶偵峚懌偱偒傞帺屓傪帩偭偰偄傞偑丄変乆偼崱偺惗妶偵枮偨偝傟傞偙偲側偔丄枮懌偺僑乕儖傪抦傜側偄傑傑丄師乆偲梸媮傪枮偨偦偆偲偟懕偗偰偄傞丅偟偐偟丄偄偔傜媮傔偰傕帺屓偺枮懌傪摼傜傟側偄偽偐傝偱側偔丄懠傪媇惖偵偟懕偗偰偍傝丄偦傟偑帺慠攋夡傗幮夛栤戣偲側偭偰丄帺屓偵娐偭偰偒偰偄傞偙偲偵傕婥偯偐側偄偱丄旐偭偨旐奞偺傒傪攔彍偡傞偙偲偵桇婲偵側偭偰偄傞丅梀杚柉偑壗傕朷傫偱偄側偄栿偱偼側偄偟丄斵摍偺幮夛惗妶偵傕攏偵偐傢傞僶僀僋傗丄儔僋僟偵偐傢傞僩儔僢僋傕擖偭偰偒偰偄傞偑丄攏偱廫暘側偙偲傪柍棟偵曄偊傞偙偲偑壗偺僾儔僗傪傕偨傜偟丄壗偺儅僀僫僗傪旐傞偐傪摢偱偼側偔丄敡偱姶偠偰偄傞偺偱偼側偄偩傠偆偐丠僶僀僋偼攏傛傝憗偄偑丄攏側傜戝抧偵惗偊傞擭傪怘傋偝偣偰偄傟偽摥偄偰偔傟傞偟丄巕嫙傪惗傔偽傑偨怴偟偄僇偲側傝丄巰傫偱傕戝抧偵娐傝丄憪傪堢偰傞丅僶僀僋偼僈僜儕儞傪攦傢側偗傟偽側傜側偄偟丄夡傟傟偽廔傢傝偱丄偟偐傕桳尷側岺僱儖僊乕偺徚旓偱偁傝丄戝抧偵娐傝偯傜偄暔幙偱偁傞丅偟偐傕偦傟傪摼傞偨傔偵偼壱偑偹偽側傜偢丄偦偺堊偵壠抺偺摢悢傪憹傗偟丄懡偔偺暔幙傪帩偰偽堏摦偑戝曄偵側傝丄梀杚惗妶偦偺傕偺偺崻杮傪愨偮偙偲偵側傞丅梀杚柉偼傎偲傫偳僑儈傪弌偝側偄偲偄偆丅偙傟偼暿抜娐嫬堄幆偼崅偄偐傜偱偼側偔丄僑儈偑弌側偄偐傜偩丅儔僕僆偺姡揹抮傪暯婥偱偦偺曈傊幪偰偰偄傞傜偟偄偑丄斵摍偺惗妶偑惗傓傢偢偐側僑儈偼姲戝側戝帺慠偑嫋梕偡傞悘埻偺傕偺偱偁傝丄帺媼偱偒側偄傕偺傪嬌椡傕偨側偄偱丄偁傞傕偺傪嵟戝尷妶梡偟偰偄傞惗妶偵偍偄偰僑儈偼弌側偄丅嶳梤丄梤偺暢偼僎儖偺彴壓偺搤偺抐擬嵽傗擱椏偵側傝丄媿暢偼壠抺偺杊晽嶒偺寗娫傪杽傔丄恖暢傕曋強傪帩偨側偄偺偱丄僎儖偺廃傝偺戝抧偵娨尦偝傟偰備偔丅偦傟偵斾傌偰変乆愭恑埻偲偄傢傟傞恖乆偺惗妶偐傜偼丄戝検偺僑儈偑攔弌偝傟丄暔偑僑儈偲側傝攑婞偝傟傞偙偲偱丄怴偨側惗嶻傪惗傒丄寉嵪偑棳傟傞丅峏偵偙偺徚旓宱嵪傪戝帺慠偲嫟偵惗妶偡傞梀杚柉傗搑忋崲偺惗妶幰傊偲峀傔丄帺暘払偺宱嵪偺僔僗僥儉傪堐帩偟傛偆偲偟偰偄傞丅傕偪傠傫丄崱巹払偑傒傫側撍慠丄梀杚柉偺曢傜偟偵曄傢傞偙偲偼偱偒側偄丅偟偐偟丄変乆偑娫堘偄偵婥晅偄偰偄傞側傜偽丄偦偺娫堘偄傪斵扗偵墴偟晅偗偨傝丄変乆偺曢傜偟偵嬤偯偔偙偲偑丄岾偣偵側傞偙偲偩偲丄閤偡傛偆側恀帡偩偗柤偼怲傒丄斵摍偺惗妶傪懜傉怱傪帩偪丄変乆偙偦偑斵摍偵嬤偯偔搘椡傪偡傞偙偲偑惓偟偄慖戰偱偼側偄偩傠偆偐丅拑楬傔傫梤杚応偱偼恀帡帠偐傕偟傟側偄偑丄梀杚擾偺惗妶傪梀傃姶妎偱庢傝擖傟偰偄偔丄拠娫偯偔傝丄柤晅偗偰 乮晲摗丂峗巎乯
丂 |
|
丂仧偼偠傔傑偟偰丅崱擭偺嬨寧傛傝拑楬傔傫梤杚応偱幚廗傪偟偰偄傑偡r帞偄尒廗偄乿庰堜怢屷偲尵偄傑偡丅 乮庰堜怢屷乯 偔曇廤晹傛傝亜 丂 |
|
仠儔儉儗僞乕10崋摿暿婇夋偦偺1仠 乣乣乣乣乣梤抝偲巹乣乣乣乣乣 尨栄壆僗僺儞僴僂僗億儞僞丂杮弌傑偡傒 丂巹丄偙偲尨栄壆偺億儞僞丅偦傕偦傕晲摗孨偲偺側傟愼傔偼斵偐傜偺擬楏側儔僽儗僞乕偵偼偠傑傝傑偡丅乽梤偵嫸偭偨儎儘乕偼丄擔杮拞偱巹堦恖偲巚偭偰偄偨傜嫗搒偵傕偆堦恖偄傞偱偼側偄偐両杮弌傑偡傒乮亖億儞僞乯敪峴偺僗僺僫僢僣傪乮亖庤朼偓偵柌拞偵側偭偨僗價僫乕偺偨傔偺忣曬岎姺嶨帍乯尒偰丄媫偓庤巻傪偟偨偨傔偨師戞偱偡丅乿偲偄偆偺偑帠偺偼偠傑傝丄廫悢擭慜丅 丂偝偰両偙偺晲摗孨偺枺椡偲偼乧 嘇偄偮傕曄傢傜偸僩儗僷儞巔丄偟偐偟杮恖偵尵傢偣傞偲丄偍弌偐偗梡丄晛抜拝梡丄栰椙巇帠梡乧偲巊偄暘偗偰偄傞乨傜偟偄丅 嘊偛懚偠丄撍慠敋徫偡傞斵丄僽僢僴僴僴僴両 嘋垽沢偁傞嶰枃栚敿丅惓柺偐傜尒偨傜丄傑偠傔側抝丅屻傠巔偼丄垼廌昚偆梉擔偺梤帞偄丅 嘍側傫偲偄偭偰傕晲摗愡偺偙傇偟偑偆側傞儐乕儌傾偁傆傟傞暥復偼丄偙偺傑傑暥昅嬈偵偝偣偨偄傎偳丅 丂亅偦偆丄彂偗偰乮暥乯丒帞偭偰乮梤傪乯丒嬳偗傑偔傞乮儚乕僋僔儑僢僾偵塩嬈偵乧乯丅亅 仠曇廤晹偐傜傂偲偙偲 仢僗價儞僴僂僗億儞僞丂嫗搒巗杒嬫摍帩堾撿挰46 丂 |
| 仠儔儉儗僞乕10崋摿暿婇夋偦偺2仠
乣乣乣乣乣10崋偍傔偱偲偆乣乣乣乣乣 僩儔僢僩儕傾丒儔丒儁僐儔丂丂僆乕僫乕僔僃僼丂壨撪丂拤堦 丂仠巹偼尰嵼僩儔僢僩儕傾丒儔丒儁僐儔乮僀僞儕傾岅偱堦旵偺梤乯偺僆乕僫乕僔僃僼偱偡丅梤偲偐偐傢傝弌偟偰乧乧寁嶼偡傞偺偑戝曄丅僐僢僋傪巒傔偰傕偆25擭丅埉愳巗偺梤娭學偺夛幮偵3擭乽僓Z儔乕乿乽戧愳巗撪偺儗僗僩儔儞乯偵偰4擭丄偦偟偰丄儔丒儁僐儔傪巒傔偰9擭丄寁16擭掱偵側傞丅晲摗偝傫偑傔傫梤杚応傪巒傔偰13擭偲偺偙偲丅偍屳偄挿偄擭寧偱偡偹丅梤偲偐偐傢偭偰偄傞帠偱偳偙傑偱敪揥偡傞偐偲巚偄偒傗丄僱僢僩儚乕僋偩偗偑嫮偄鉐偲側偭偰偄傞丅撈棫偟偰9擭栚丄帺暘偺偍忛偑帩偰偨乮偡傌偰庁嬥乯丅偦偟偰娕斅偵丄摴嶻梤椏棟愱栧揦偲擖傟偨丅傗偼傝丄抧応嶻偵偙偩傢傝懕偗偨偄偑堊丅偙傫側偍偄偟偄擏傪彮偟偱傕懡偔偺恖偵抦偭偰傕傜偄偨偄偑堊丅帺暘偺揦偺墶偵偼儔儀儞僟乕傪怉偊丄懡偔偺恖偵尒偰傕傜偄偨偄偲巚偄丄帺暘偺敤偱堢偰偨僴乕僽傗丄栰嵷傪偍揦偵弌偡丅奆丄婌傫偱偔傟偰偄傑偡丅 仢僩儔僢僩儕傾丒儔丒儁僐儔丂杒奀摴戧愳巗杮挰2挌栚 丂 |
 仧拞壺偪傑偒仧 仧拞壺偪傑偒仧
婥帩偪偺偄偄擔丄偍曎摉偱傕帩偭偰偳偙偐傊弌偐偗偨偄婥暘丅 |