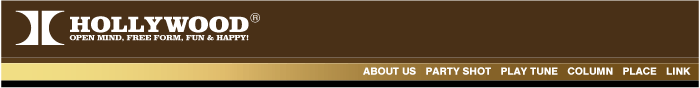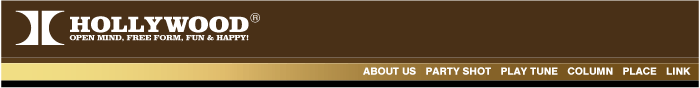コラムのコーナーではお久しぶりです。オーガナイザーの山本です。
まずお詫びを一つ。先月のWEB定期更新の遅れ、及びCROSSOVER COOKIN'の休載本当にすみませんでした。 実は仕事でぎっくり腰をやらかしてしまい、約2週間まったく使い物にならない状態だったのです。今ではすっかり完治して、レンジライフの1周年パーティーにも無事参加できることになり、心からホッとしています。
しかし、ぎっくり腰と聞くと人はなぜ心配より笑いが先に出てしまうのでしょう?(笑)。「アキレス腱を切った」とか「肺に穴が開いた」と言えば本気で心配するのに、ぎっくり腰ならまず爆笑。語感のせいなのか、ぎっくり腰ってなんかコミカルですよね。
まあ、それはともかく。療養中は意識がピンピンしているのにも拘らず、身体は全くいうことを聞かないので、気が狂いそうになるくらい暇。ベッドからも起き上がることができなかったので、寝るとき以外は本を読んでばかりいました。
そこで夢中になったのが、この「河出書房新社 世界文学全集」。
まず、みなさんは「世界文学全集」という響きにどのようなイメージを抱くでしょうか?よほどの読書家でもない普通の人は「存在は知っているけど、自分とは全く関係のないもの」という位置づけだと思います。かくいう僕も、あるときは図書室の隅で誰からも気付かれることなくジッとしているものだったり、またある時は一昔前のちょっとインテリを気取ったお父さんの書斎の本棚でこれまたジッとしている―というイメージがありました。装丁もソフトカヴァーなしの味気ない布表紙で、見るからに手強そう。
そもそも世界文学全集というものは、教養主義的思想がはびこっていた戦後から80年代くらいまでの間に上記のお父さんの例のように「読んでいないと恥ずかしい」、「本棚にとりあえず並べておきたい」という、本来の読書の魅力からはかけ離れた「背表紙の文学」だったらしく、それはそれでそこそこの売り上げがあったらしいのですが、教養主義も崩壊した90年代以降は下降の一途を辿る一方で、今回の河出が何と18年ぶりの世界文学全集発刊という、それはそれは出版業界に激震が走るニュースだったのです。
そんな無謀としか思えないチャレンジを試みた河出ですが、出版業界の予想に反してこれがなかなか好調な売り上げを見せているようなのです。
もちろん売れない世界文学全集を今の世に放つということは、今の世に即したかたちで出さなきゃいけないわけですが、まず見て下さい上の写真。装丁がものすごくスタイリッシュでしょう?これなら女の子がカフェで読んでも恥ずかしくない(笑)。僕もこの装丁じゃなく、それこそ旧来の味気ないものだったらまったく興味をそそられなかったと思います。
 もう一つの新境地は全24巻36作品のセレクトを作家の池澤夏樹一人が手掛けているということ。普通、世界文学全集といったらクラシック、というか絶対的な評価がある作品で揃えられるように思いますが、編者がたった一人ということはセレクトの基準も個人の思い入れを含めた極めて主観的なものにならざるをえなくて、「何であの作品が入ってないんじゃ!?」ということになるでしょう。ラインナップの中にはそれこそサガンの『悲しみよこんにちは』などの不朽の名作も収録されていますが、それよりも初訳、即ち初めて日本向けに翻訳された作品の多いこと多いこと。つまり絶対的な評価がない作品、知る人ぞ知る作品、今まで日の目を観ることがなかった作品でも「いいものはいい」という価値観でスポットを当てているということです(驚くことに収録作の中には池澤夏樹本人が読んだことのない作品までもが!笑)。
もう一つの新境地は全24巻36作品のセレクトを作家の池澤夏樹一人が手掛けているということ。普通、世界文学全集といったらクラシック、というか絶対的な評価がある作品で揃えられるように思いますが、編者がたった一人ということはセレクトの基準も個人の思い入れを含めた極めて主観的なものにならざるをえなくて、「何であの作品が入ってないんじゃ!?」ということになるでしょう。ラインナップの中にはそれこそサガンの『悲しみよこんにちは』などの不朽の名作も収録されていますが、それよりも初訳、即ち初めて日本向けに翻訳された作品の多いこと多いこと。つまり絶対的な評価がない作品、知る人ぞ知る作品、今まで日の目を観ることがなかった作品でも「いいものはいい」という価値観でスポットを当てているということです(驚くことに収録作の中には池澤夏樹本人が読んだことのない作品までもが!笑)。
さらには小説以外にも紀行文学やエッセイなどジャンルの括りがない構成、欧米の先進諸国以外の、例えばベトナム、チェコ、旧ソ連、ペルー、中国…など、あまり馴染みのない国の文学までもを擁した縦横無尽なパースペクティブ…。こういった主旨を聞くと、DJやクラブ・ミュージック・ラヴァーは何かを連想しませんか?
そう、これは「文芸版レアグルーヴ」なんですよ。
レア・グルーヴ(レア・グルーヴ・ムーヴメント)とは80年代のロンドンで生まれたもので、それはそれまで中古レコード屋で隅っこの100円エサ箱にひっそりと置かれていたような、誰も見向きもしなかったレコードに光を当て、新しい価値を見出し、それをダンス・ミュージックとして活用する、という「価値観の逆転」を主に置いたムーヴメントでした。
レア・グルーヴの登場によって音楽の価値観が刷新されてしまったように、この世界文学全集も今後の文学の在り方を変えてしまう可能性も無きにしも非ずではないでしょうか?そしてレアグルーブ以降の若き本読みたちがこの思想をカッコイイ!と思い、本書を手に取るようになったらそれはたまらなくクールなことです。
この世界文学全集もレア・グルーヴも、「権威に翻弄されず、安心さに擦り寄らず、唯一のモノサシは他でもない自分」という精神が宿っています。それはカウンター・カルチャーと言い換えても。
まあそんなわけで、とりあえず第一弾「オン・ザ・ロード」(ジャック・ケルアック著)を読んでみました。本書は20世紀半ばにアメリカに台頭した「ビート・ジェネレーション」を代表する文学で、あのボブ・ディランが「私の人生を変えてしまった一冊」と評したり、フランシス・フォード・コッポラ(ソフィア・コッポラのお父さん)が映画化に着手してはみたものの、思い入れが強すぎて10年経った今でも未だ未完成、という逸話を持つ「アメリカの青春文学の金字塔」とも呼ばれる作品です。
ユース・カルチャーに少しは関心のある人ならば一度はビート・ジェネレーションという言葉は聞いたことがあるように思いますが、恥ずかしながら僕はそれが何なのかさっぱりわかりませんでした。ウィリアム・バロウズという人が何となくそれに関係した人なんだろうな、あとはドラッグとか?酒とか?野村訓一?(笑)くらいの認識です。
まあビート・ジェネレーションの解説はググってもらうことにして、簡単なストーリーはこう。この話は著者の実体験を基にして書かれていて、主人公のサル(著者ケルアック)が友人ディーンに惹かれるままに、アメリカ全土を何度も横断、縦断する、といった放浪記です。
一通り読み終えてみての感想は、とにかくわけがわからない!!といった感じでした。まず既存の紀行文学と違ってサルとディーンの超が付くほどいい加減な二人の旅には、全くもってテーマも意味も目的もない。「自分探し」もしない(だって自分ここにいるしねぇ?)。サンフランシスコ、デンヴァー、ニューメキシコ、シカゴ…どこにいようがやることは酒、女、ドラッグ、どんちゃん騒ぎの繰り返し。ストーリーらしいストーリーもありゃしません。青山南の訳も意訳をあまりしていない(と思う)ので読んでてすごく引っかかる。ゆえにページが遅々として進みません。そして一番わからないのが常に躁状態のディーンのキャラクター。狂ってるとかキ○○イとかじゃ済まされない。こんなとんでもないキャラクターは今まで見たことがない。しかし、このわけのわからなさ全部がなぜかすごく気持ちよくて。わからないけれども全編を疾走感と躍動感が凄まじい濃度で押し寄せてくるのです。
こんなにも??が多いのに、こんなにも強い印象を残した小説は今までありませんでした。やっぱり読書も音楽も映画も、表現と呼ばれるものは何でもそうですが、「わかりやすい=善、わかりにくい=悪」という図式ははっきり間違っているということです。今の世の中では誰でも簡単に共感できて、感動できて、泣けて…という表現しか受け入れられなくなっているような気がします。みんなそんなに泣きたいの?という気もしますけども…。そういう期待通りの感情を得て満足して、はいおしまいって、池澤夏樹の言葉を借りればそれは「消費」に過ぎないんじゃないかなって思うんですよ。喉渇いたからコンビニでジュース買うってのと一緒。本も音楽も本当の快楽はそこじゃなくて、自分の予想や理解を遥かに超えたとんでもないものとある日突然出会うからこそおもしろいのだし、心に残るんじゃないでしょうか。またそうするしか世界というものは広がっていかないとも思います。
今後この世界文学全集は今後約2年間に渡って全24巻が配本されます。全巻揃えると総額は何と¥66,360…。何とも忍耐の必要とする額ですが、これらを読むか読まないかで今後の人生も多少左右されるかもしれないので士気は高めに!って感じでしょうか。
河出書房新社 世界文学全集特設サイト
http://mag.kawade.co.jp/sekaibungaku/