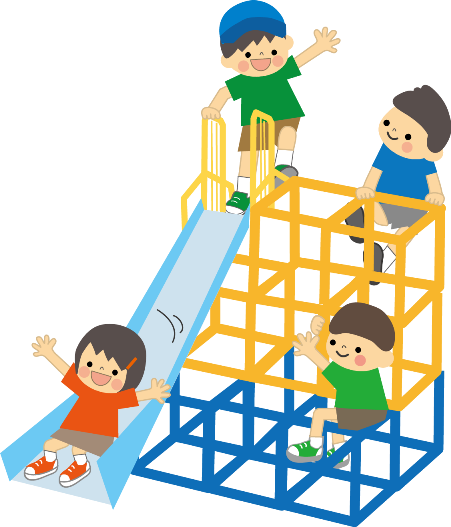|
問題25 公園で泣きながら戻って来た我が子にかける言葉は? |
|
女の子が悲痛な叫び声を上げて泣いたのは叩かれたことが痛かったからではないのです。女の子は泥のおまんじゅうを上手に、きれいに作り上げてうれしかったのでしょう。ごっこ遊びというのは空想と現実が交じり合った世界です。上手に作ったおまんじゅうをお母さんに食べさせたい、プレゼントしたいと思い、ホクホクした気持ちで見せに来たのでしょう。ここには「一人で上手に作り上げた」という達成感があり、「お母さんにプレゼントしたい」という子どもなりの愛情があり、さらには「これをプレゼントしてお母さんからほめられたい」という愛情を受け取りたいという気持ちが入っています。それなのにこのお母さんは、その情を受け止めることなく一瞬で否定していまいました。そのショックで女の子は号泣したのです。 |
|
|
愛情深い受け止め方はどうあるべきでしょうか。 |
|
【答え】 |
「どうしたの」「お母さんはここよ」など |
|
出題のポイント |
情の受け止め方は様々考えられます。この子は、お母さんを求めて戻って来たわけですから、その気持ちを受け止める言葉なら何でもかまいません。「はい。お母さんはここよ!」でもいいですし、「はい、はい。どうしたの」でもいいでしょう。この場合の「どうしたの」は、答えを聞き出そうとしているというよりは、泣いている気持ちをなぐさめるための「どうしたの」だと思います。ですから「知」というよりは「情」の言葉になります。他にもいろいろ考えられると思いますが、肝心なのは泣いている気持ち(怖い・悲しいなどの不安)を受け止める言葉になっているかどうかです。 |
|
「どうしたの」「お母さんはここよ」などと言って我が子を抱きしめてあげるだけで、大抵は満足して(愛情をもらって勇気満タンになり)、また自分から砂場に戻って行くものです。そして、しばらくするとまた泣いて戻って来る。また「どうしたの」「お母さんはここよ」と言って抱きしめてやる。そういうことをくり返しているうちに、いつまで経っても戻って来なくなって、しまいには「帰るよ」と言っても「やだ」と言うくらいに慣れてしまう―――これを「飛行場現象」と呼ぶ場合もあります。母親という燃料補給基地で愛情という燃料を満タンにしてもらえれば、しばらくは飛んでいられるという現象です。精神分析学者のボウルビィは、このような母親の機能を「安全基地」と呼びました。これは、母親が子どもにとって安心できる存在として確立していることを証明する現象でもあり、自分ひとりで行動することを増やしていくときの通り道です。自立へのステップであり、愛着形成の最終ステージでもあります。 |
|
[23]坂東義教『坂東先生の教育講座』(テレビ朝日)12-22 |
|
|
|